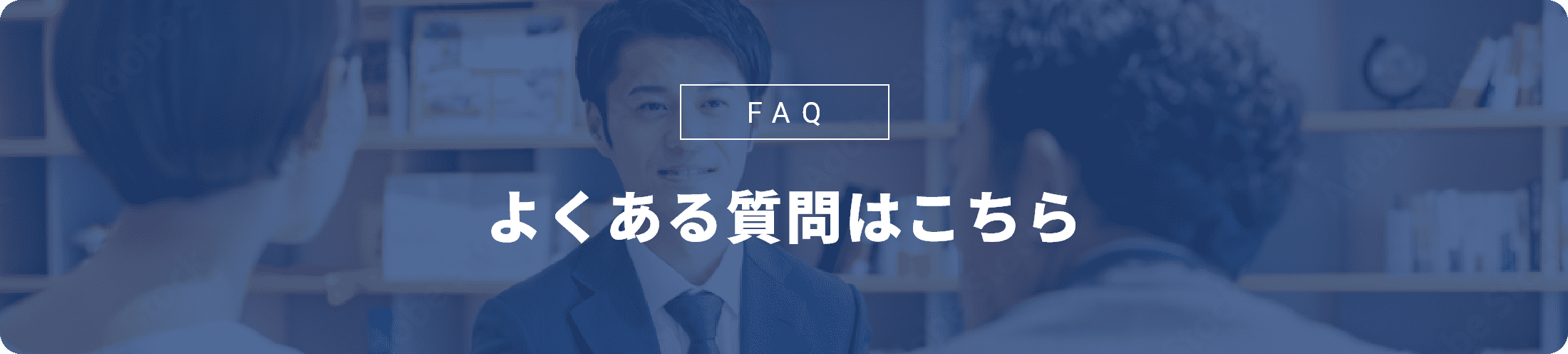相続税の基礎控除
実際に遺産を相続する時に、税金ってかかるの?と疑問を抱く方もおられるでしょう。
この記事では、どのような方が相続税申告が必要なのか、相続税基礎控除についてご説明します。
基礎控除とは
そもそも相続税とは、被相続人(亡くなった人)から相続や遺贈によって財産を取得した際に
課される税金のことです。
相続税の基礎控除は、相続税の計算で用いられる非課税枠を指し、
相続した遺産が基礎控除額以下であれば申告は原則不要です。
なので基礎控除額の計算方法が重要になります。
基礎控除額の算出方法

基礎控除額の計算は法定相続人の人数が分かればすぐ計算できます。
3000万円 + (600万×法定人数)=基礎控除額
基礎控除額は最低3600万円です。
法定相続人が二人ならば4200万円と、一人ずつ増えると600万円増えていく仕組みです。
つまり、3600万円以上の財産があれば相続税は発生し相続税申告が必要になります。
また、基礎控除額が3600万以上に当てはまった場合、
全ての相続に税金がかかると勘違いされがちですがそうではなく、
相続税は控除額をオーバーした部分しか課税されません。
例えば、被相続人が配偶者・母と子供2人を残して死亡し、遺産が8,000万円あった場合を考えます。
基礎控除額 の計算 3000万円×600万×3(人)=4800万円
↓
課税遺産総額の計算 8000万円 – 4800万円=3200万円
母の場合、3200万円×1/2(法定相続分)×15%(相続税率)ー控除額(50万円)=190万円
母の発生する相続税は190万円となります。
課税遺産総額を計算するには、まず基礎控除額から計算になるので重要になってきます。
基礎控除額が超えても税金が発生しないケース
基礎控除額を超えると、必ずとも相続税が発生するわけではありません。
基礎控除には他にもさまざまな特例があります。
①配偶者の相続税控除
法定相続人が配偶者であれば特別な控除が適用されます。
適用内容は以下二つです。
・配偶者の相続額が1億6000万円以下なら相続税が課税されない
・配偶者の相続した財産が1億6000万円以上だとしても、法定相続分までなら課税されない
例えば、相続人が配偶者と子1人の場合、配偶者の法定相続分は1/2です。
仮に遺産総額が1兆円、配偶者が法定相続分の5,000億円の遺産を相続しても
法定相続分なので課税はされません。
②未成年控除
未成年者が相続する場合、その扶養義務者が扶養する期間に応じて控除が適用されます。
控除額:10万円×(20歳−相続開始時の年齢)
例えば、10歳の子供が相続する場合、10万円 × (20歳 – 10歳) = 100万円の控除されます。
③障害者控除
障害者が相続する場合、その障害者の年齢に応じて控除が適用されます。
控除額:10万円×(85歳−相続開始時の年齢)
例えば、50歳の障害者が相続する場合、10万円 × (85歳 – 50歳) = 350万円の控除されます。
④暦年課税分の贈与控除額控除
相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合、その贈与税額を相続税から控除できます。
⑤小規模宅地などの評価減の特例
被相続人が居住していた宅地や事業用地について、
一定の要件を満たす場合に評価額を減額できる特例です。
・居住用宅地: 最大330㎡まで80%減額
・事業用宅地: 最大400㎡まで80%減額
例えば、被相続人の自宅の土地が300㎡であれば、その評価額の80%が減額されます。
⑥相次相続控除
短期間に相次いで相続が発生した場合に、前回の相続にかかった相続税を控除できる制度です。
相次相続税額 × 相次相続割合 × 法定相続分割合
10年以内に再度相続が発生した場合に適用されます。
まとめ
遺産相続の税金は、基礎控除を適用することで減額が可能です。
基礎控除額を超えても税金がかからないこともあるため、
控除制度や特例をしっかり確認しておきましょう。
不安な方は、相続に詳しい税理士や遺産整理業務に力を入れる金融機関への相談を
検討してみてください。